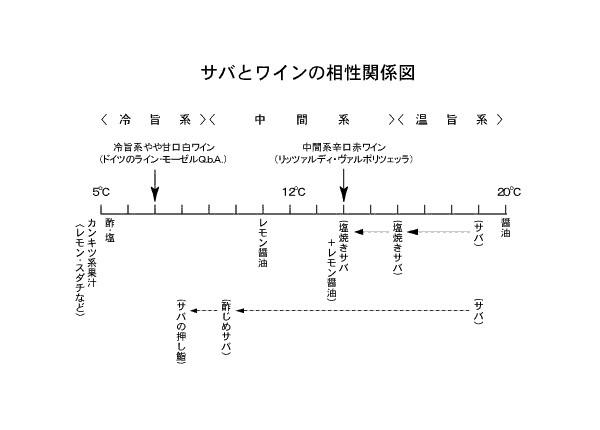〜相性のピタピタ原則〜 【2】)
前回は、「サンマ」をテーマに、「ワインの飲用適温」を中心に述べ、ワインには大別して(1)冷旨系(2)温旨系(3)中間系の3つのタイプがあることを解説しました。
今回は、「ワインの原点」と「ピタピタ理論の要点」をとりあげながら、「ワインの飲用適温と料理との相性」について考えてみます。
昔から「ワインの飲用適温と料理との相性」については、単に経験的に取り扱われてきただけでした。つまり、共通の尺度がないまま、”ああでもない、こうでもない”といわれてきて、ただただ混乱するばかりでした。
ここで「ワインの原点」と「ピタピタ理論の要点」をよく理解していただき、それを実際に体験していただければ、毎日の食卓の楽しさが倍増することはまちがいありません。
その実際の応用編としては、「サバの塩焼き」と「サバの押し鮨」について、「相性のピタピタ原則」の考え方に従って解説します。
<ワインの原点>
ブドウの一粒は果皮、種子、果肉からできています。これがワインの原点です。果皮には色素とタンニンなど、種子には油脂分とタンニンなど、果肉には水分、糖、有機酸(酒石酸とリンゴ酸がほとんどで、クエン酸は微量)、ミネラル分などが含まれています。
これらの諸成分のうちで、ワインのタイプと個性を鮮明にあらわす要素が有機酸なのです。原料ブドウに含まれる酸は「酒石酸とリンゴ酸」であることを、よく記憶に留めておいてください。
<「ピタピタ理論」の要点>
「ワインの飲用適温と料理との相性」を私は通称「ピタピタ理論」と名付けています。この「ピタピタ理論」の根底には、「ワインも料理(食材・調味料)も食品の一つである」という考え方があります。そして、ワインや食材は、次の4つの条件で微妙に変化します。
(1)運動によって生ずる疲労
(2)空気中の酸素によって生ずる酸化
(3)微生物などの作用
(4)加熱
こうして、食品は最初の「さわやかな旨み」から「コクのある旨み」へと変化し、日数が相当経過した場合には、さらに「苦みや刺激味のある成分」へと変化していく経路があります。
つまり、食品の成分は、常に一定ではないということなのです。
この考え方に基づいて、食品はおおまかに3つのタイプにわけられます。
A(冷旨系) → B(中間系) → C(温旨系)
生まれたてのもの やや年季が経ったもの 相当、年季を経たもの
あまり運動しないもの やや運動するもの 長時間運動するもの
葉っぱ状のもの など やや顆粒状のもの など 顆粒(果実)状態のもの など
これらは、AからBへ、BからCへ変化していきます。そして、一般的にAは「冷やしておいしい」ので冷旨(レイシ)系、Bは「ほどほどに冷やしておいしい」ので中間系、Cは「室温ぐらいでおいしい」ので温旨(オンシ)系と呼ぶことにしました。
さて、ワインと料理がピタピタと相性よく合うためには、ワインも上記のような食品成分の変化に対応していく必要があります。溶剤の化学では「似たものは似たものをよく溶かす」といわれています。例えば、「水とエチルアルコールは溶けやすく、水と油は溶けにくい」などのことをあらわしているわけです。この原則は、ワインを含む食品全般に当てはまるといえましょう。
後日解説いたします「ワインと料理の相性表」は、食品間で似た物質の成分、あるいは相性の良い成分は仲が良いことを示しています。このことは、さらに食品間の初期に生成される成分同士、中期に生成される成分同士、後期に生成される成分同士は非常に相性がよいことを強く示唆しています。
こういった変化に対応して、ワインと食材がもっとも仲のよい時期の両者を選べば、すばらしい味覚の世界が広がってくるはずです。このことを、各単一成分間の多くの実験を通して、実証したのが、「ピタピタ理論」なのです。
もし、ワインと食材の相性が今一歩のときには、調味料が調整役としてその役割を果たします。そのために、相性表では、各調味料のタイプ分けも行いました。
それでは、応用編へまいりましょう。
秋。サバのおいしい季節です。
今回は、調理法のまったく違う二つの料理「サバの塩焼き」と「サバの押し鮨」を取り上げて、それによく合うワインの相性診断をしてみましょう。
(1)サバの塩焼き
さて、前回のサンマと同様に、サバを焼く前にあらかじめ「ふり塩」をします。これで、魚肉が食塩で固まり、焼いたときに身くずれが起きにくくなります。同時に、塩の強い浸透圧によって、サバの細胞内から乳酸や生臭み成分もかなり吸い出されます。さらに、焼くことによって油分、乳酸などの成分がいくらか取り除かれ、ややさっぱりとした魚肉に変わってきます。
ところで、サバの魚肉には魚介類の仲で最も乳酸が多く含まれています。(684mg/100g)この量は、乳酸の多いボルドー赤など、温旨系ワインの約2〜3倍にもなります。また、旬のサバには油分も多く含まれています。(16.5g/可食部100g)
つまり、旬のサバは、乳酸・油分の多い肉質の典型的な温旨系食材なのです。
一方、温旨系調味料の典型である醤油に含まれている乳酸の量は、約1946mg/100mlと、サバよりやや多めです。魚介類の中で焼き立てのサバがほかの魚よりも醤油に一番合いやすい理由は、この辺にあります。
では、醤油をかけるだけよりも、もっとおいしく食べるにはどうしたらよいでしょうか?ここで登場するのが、カンキツ系果汁(レモン、スダチなど)です。焼き立てのサバの身を少しほぐし、これにレモン醤油(普通の辛口醤油にほぼ同量のレモン汁を絞ったもの)をかけます。すると、サバの焙焼臭も消え、味は冴えてきます。
ここで、軽い赤ワインの中間系辛口赤、リッツァルディのヴァルポリツェッラを飲んでみます。口の中には一段上の旨さが広がってきます。
(2)サバの押し鮨
サバは酢に浸す前に、必ず多めの塩をふり、かなりの時間そのままにしておきます。こうすると、塩の浸透圧のため魚の体液や皮下組織の油分などが外へ吸い出され、さらに乳酸や生臭み成分もかなり取り除かれます。
その上で、酢じめをするので、酢の成分が空になったサバの細胞内に浸透し、サバの肉質をまったく変えてしまいます。特に、この酢じめは江戸前鮨の場合よりも、たっぷり時間をかけるので、「酢まわし」といわれています。
この時に、いわゆる「あんばい(塩梅)」のバランスがとられ、塩味・酸味ともに極端に強く感じられない丸みのある味に仕上げます。そして、甘酢の効いたすし飯の上に、この肉質のまったく変わったすし魚(サバ)をのせ、押しながらしめます。こうして、冷たい状態でもおいしい鮨が出来上がるのです。この押し鮨の特徴は、十分に酸味の効いた甘口基調です。つけ汁は一切使いません。
これによく合うワインは、さわやかな酸味と甘みのバランスがよい、ドイツのライン・モーゼルのQ.b.Aの白(冷旨系やや甘口・白)です。
このように、サバという同じ食材を使っても、調理方法や調味料の組み合わせにより味は異なり、ワインとの相性も微妙に変化してくるのです。